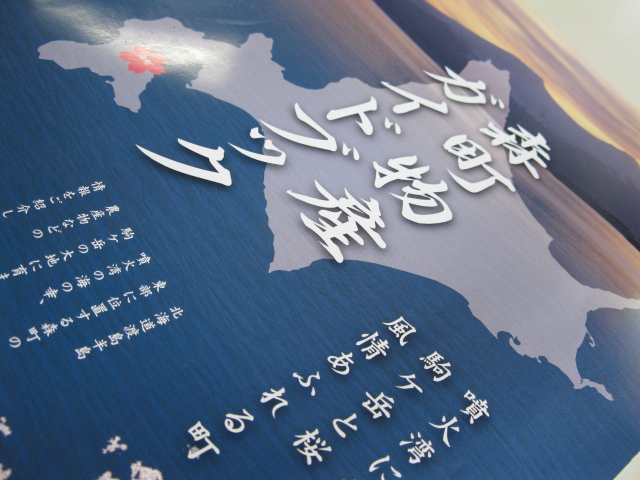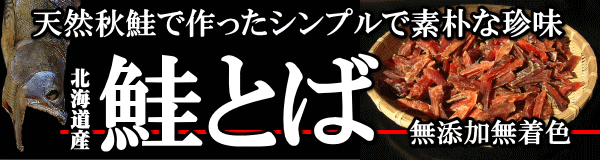厳しい気候を活かして作る棒タラ
しばれてます。
北海道の方言らいいのですが、地元民にしてみれば、なにが方言なのかぴんときません。
気温が下がり、肌を刺すような寒さ。
これに風が吹こうものなら・・・。
ですが、この寒さを待って仕込みに入る商品があります。
それは棒たら。
地元で水揚げされる新鮮なスケソウをさばき、白子、助子を取り出します。
助子は、たらこや明太子に加工されます。
タラの身は、ほとんどが蒲鉾の原料としてすり身に加工されますが、ごく一部のスケソウを棒タラとして仕込みます。
寒風にさらされるところに、乾すこと三か月余り。
夜間の凍てつく寒さで、その身は凍結。
日中の若干柔らぐ気温で、身はゆるむ。
それを繰り返し、タラの身の水分は抜け身がパサ付いてくる。
仕上がる頃には、まるで棒のように硬くなるから棒タラ。
棒タラとは、よくできたネーミングです。
棒タラは、流水でもどしてから料理に使いますが、
棒タラを金づちでたたいて身をほぐし、むしった身にマヨネーズをつけて食べるのです。
むしった状態の物がコンビニなどで売っていると思いますが、
実は、労力が必要な珍味。
働いた者だけが食べることを許される珍味です。
大袈裟ですかね。
小さな頃から、父親や近所のおじさんが棒タラをたたく後ろ姿を見て不思議に思っていたものです。
だって、魚を金づちでたたいているのですからおかしくて。
棒鱈を食べるために使う道具、金槌(かなづち)。
実は、親父が建具職人で棒鱈を食べる環境が整っていました。(笑
職人の道具なので、大工、建具、型枠、板金、鉄鋼、石工それぞれの業種で呼び名、使い勝手があり、そのうんちくを語ると異論も出そうですが、建具職人の無知な息子の金槌話を少しだけ。
金属製は、金槌。
木製は木槌。
槌(つち)とは、ものをたたく道具の事で、その歴史は古いと思います。
例えば、原始人が、木の柄に石を取り付けたアレ!
(石斧と呼ばれているけどのそ性質を考えれば・・)
棒鱈をたたくには一番絵になると思います。プププ
金槌、玄翁、ハンマー、とんかちなんて呼ばれていますが、まったく同じものではありません。
玄翁(げんのう)は、頭部の両面が平らに見えるもの。実は片面は、少し凸で、最後の釘うちの最後の仕上げに使います。打撃部を小さくすることで木材のダメージを少なくしながら釘を深く打つ。
金槌は、片面が平面で、反対側が丸かったり尖っていたり、釘抜きになっていたりと多彩で、形状によって呼び名が変わったりします。
仕事では、尖った物を使います。 釘打ちの仕上げに尖ったところで、こつんと打ち込みますが、このひと手間が、いかにも職人という感じ。
素人がマネをすると、打撃点がずれ、仕上げのつもりが商品を傷物にしてしまいます。
ハンマーは、少なくともうちの親父が、「ハンマー」と口にしたことはありません。
古い職人なので、わざわざ英語読みはしないと思います。
プラスチック製や、ゴム製は、槌とは呼ばずに、プラハンマー、ゴムハンマーと呼びますね。
とんかち・・・・・コレは金槌で釘打ちする時の擬音に由来するもので、「お~い、トンカチ取ってくれ~」なんて聞きませんね。
でも、言いたいことはわかるんです。
トンカチ取ってといわれれば、金槌渡します。
こんな感じです。